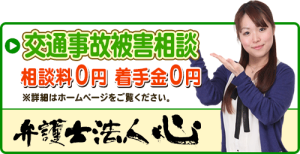交通事故
人身事故と物損事故について
1 人身事故と物損事故
交通事故を警察に届け出た場合、人身事故として扱われる場合と物損事故として扱われる場合があります。
被害者の方が亡くなったり、明・・・(続きはこちら)
交通事故の事故証明について
1 交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類になります。発行してもらうためには、警察に交通事故を届け出ている必要があり・・・(続きはこちら)
交通事故の高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害とは、事故などによって脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障・・・(続きはこちら)
交通事故の高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット
1 手続きや見通しを把握できる
交通事故被害にあい、高次脳機能障害になった場合(高次脳機能障害の可能性がある場合)、今後の対応、後遺障害等級、損害賠償など・・・(続きはこちら)
交通事故の示談金の計算方法
1 示談金の計算のタイミング
交通事故による損害は、主に、車両の修理や所持品の損傷などの物的損害(物損)と治療費や慰謝料などの人的損害(人損)に分けられま・・・(続きはこちら)
交通事故による高次脳機能障害の逸失利益
1 逸失利益とは
交通事故でケガをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害によって将来得ることができないと考えらえる利益のことを「逸失利益」といいます。・・・(続きはこちら)
無職の方の交通事故の休業損害
1 休業損害について
交通事故によってケガを負い、治療のために入院や通院が必要になったり、ケガが原因で働くことができず、休業を余儀なくされた場合、それに伴・・・(続きはこちら)
交通事故の示談で注意すべきこと
1 過失割合を確認する
交通事故にあい、車両に損害が生じたり、ケガをしたりした場合、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
示談交渉は・・・(続きはこちら)
交通事故で高次脳機能障害の疑いがある場合の対応
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やケガなどによって脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れてしまうといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱す・・・(続きはこちら)
交通事故の後遺障害の申請方法
1 交通事故による後遺障害
交通事故被害にあって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。
交通事故によ・・・(続きはこちら)